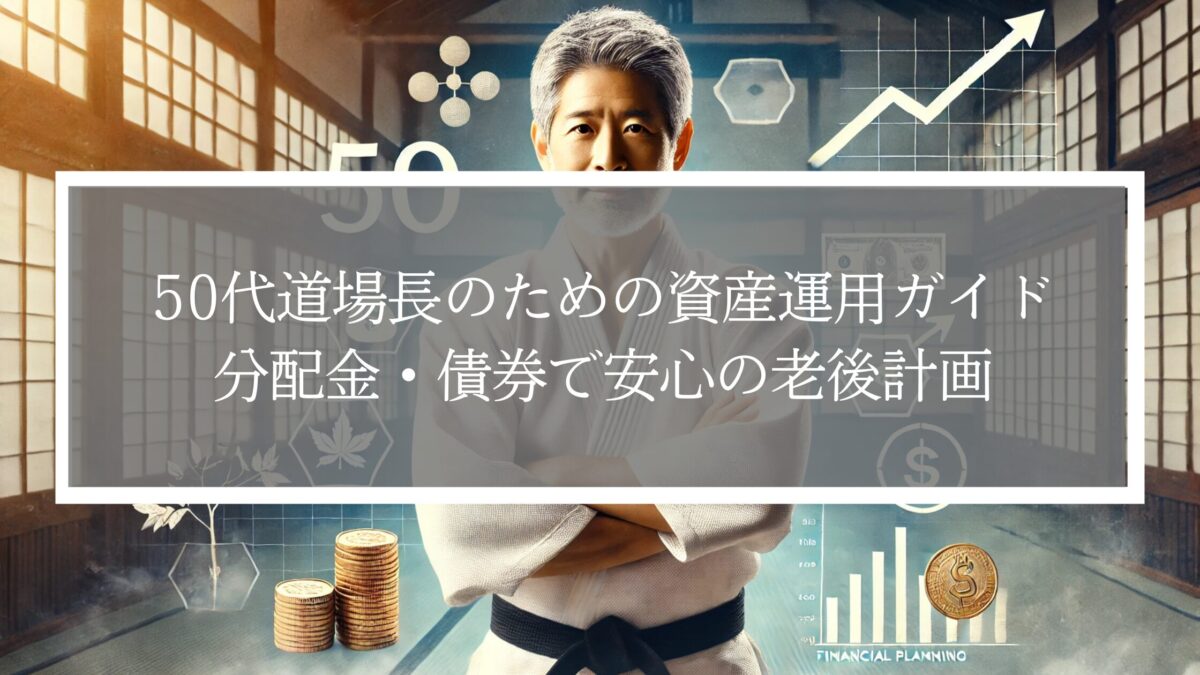50代の道場長にとって、資産運用は老後の安定と道場の経営リスクへの備えを考える重要な時期です。
この時期には、退職や収入減少に備えて、資産を安全性の高い運用商品へリバランスすることが求められます。
特に、分配金や配当金が得られる商品を取り入れたり、新NISAつみたて投資枠や成長投資枠、小規模企業共済を活用することで、老後資金の確保と安定収入を両立させることが可能です。
本記事では、資産運用の具体的な方法を対話形式でわかりやすく解説します。

- 資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本証券アナリスト協会 認定アナリスト - 略歴
大学卒業後、大手銀行のリテール部門で22年勤務。入行時から継続してきた資産運用でバリスタFIREを40半ばで達成。
現在は資産運用アドバイスなどの活動を行っている。 - 専門分野
投資、資産運用
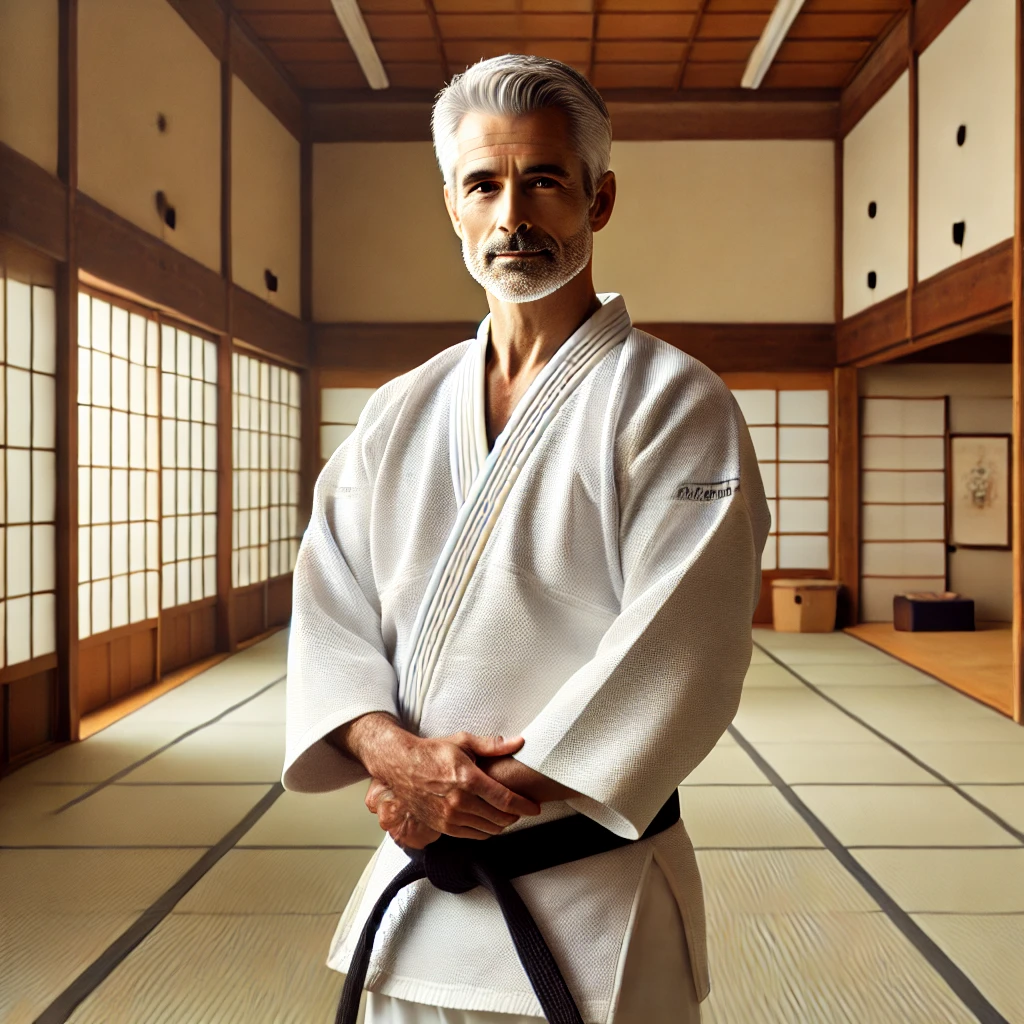
50代になり、これからの生活や道場の経営をどう安定させていくか悩んでいます。
収入も以前より減ってきたので、老後に向けた資産運用の仕方を教えてください。

50代は、資産運用の方針を少しずつ変えていく時期です。
これまでの資産形成から、安全性を意識した運用へリバランスするのがポイントになります。
また、分配金や配当金で定期的な収入を得る方法も考えましょう。
具体的な方法を順にお話ししますね。
おすすめの資産運用方法
新NISAつみたて投資枠
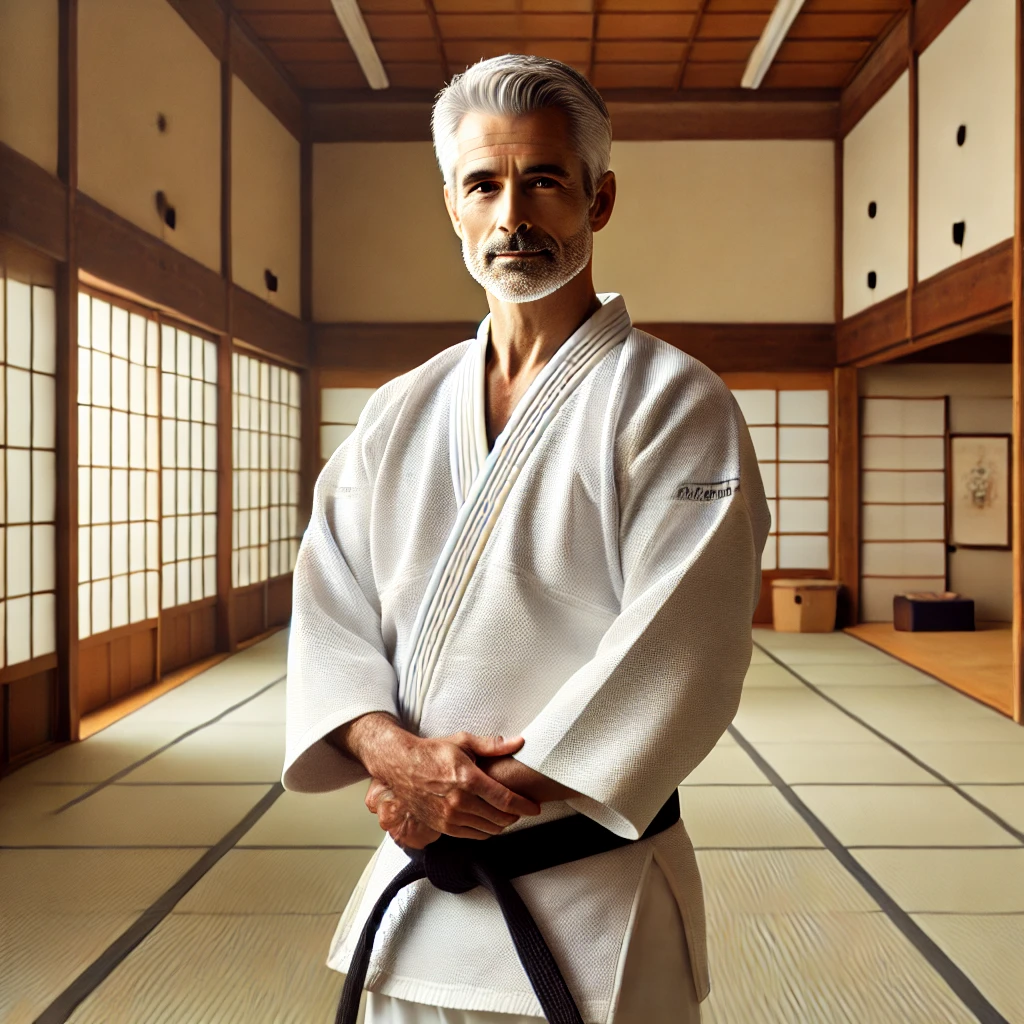
新NISAつみたて投資枠は50代でも有効ですか?

もちろんです。この枠を使うことで、年間120万円までの運用益が非課税になります。
50代から始めても、60代以降に向けて資産を育てる効果があります。
また、分散型のインデックスファンドを活用することで、リスクを抑えた運用が可能です。
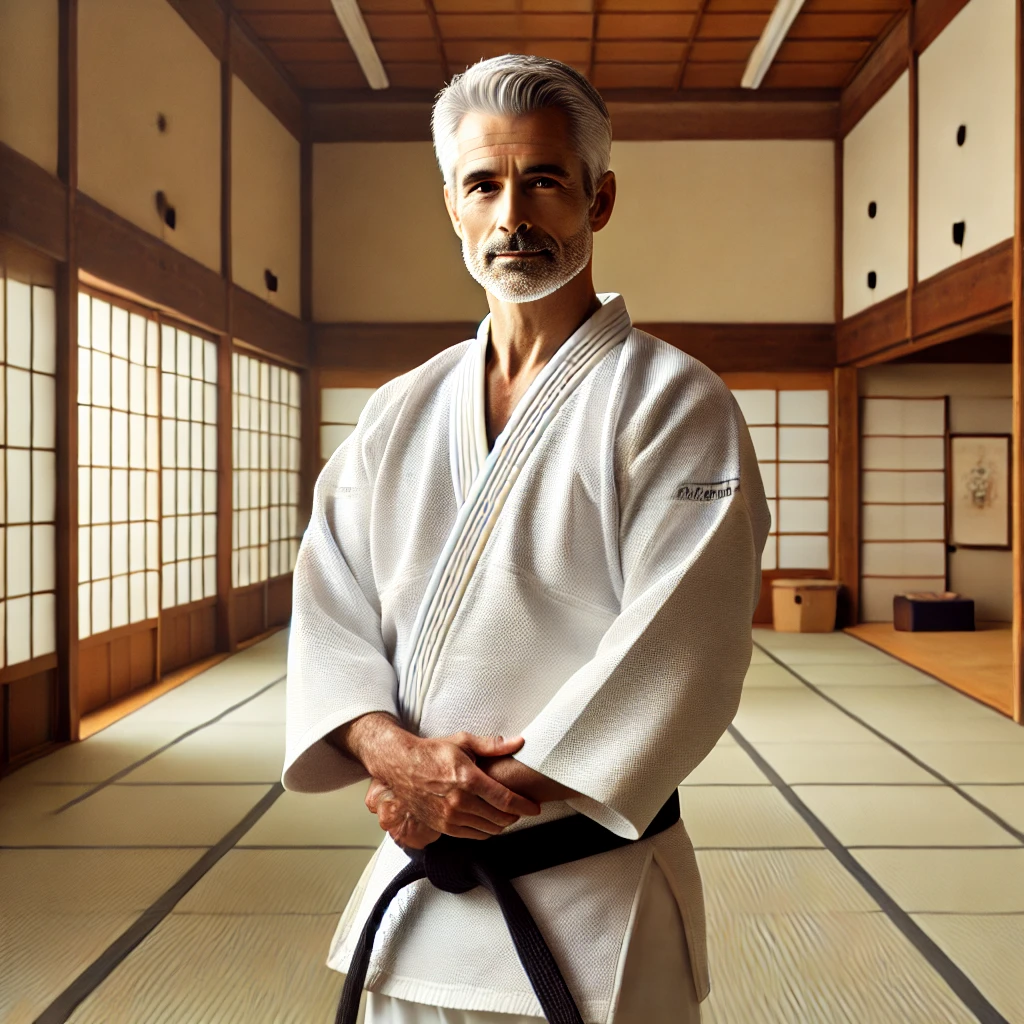
リスクが心配ですが、大丈夫でしょうか?

新NISAつみたて投資枠の対象商品はリスク分散が効いています。
さらに、毎月少額から積み立てられるので、無理なく続けられるのが特徴です。

新NISA成長投資枠と特定口座一般枠
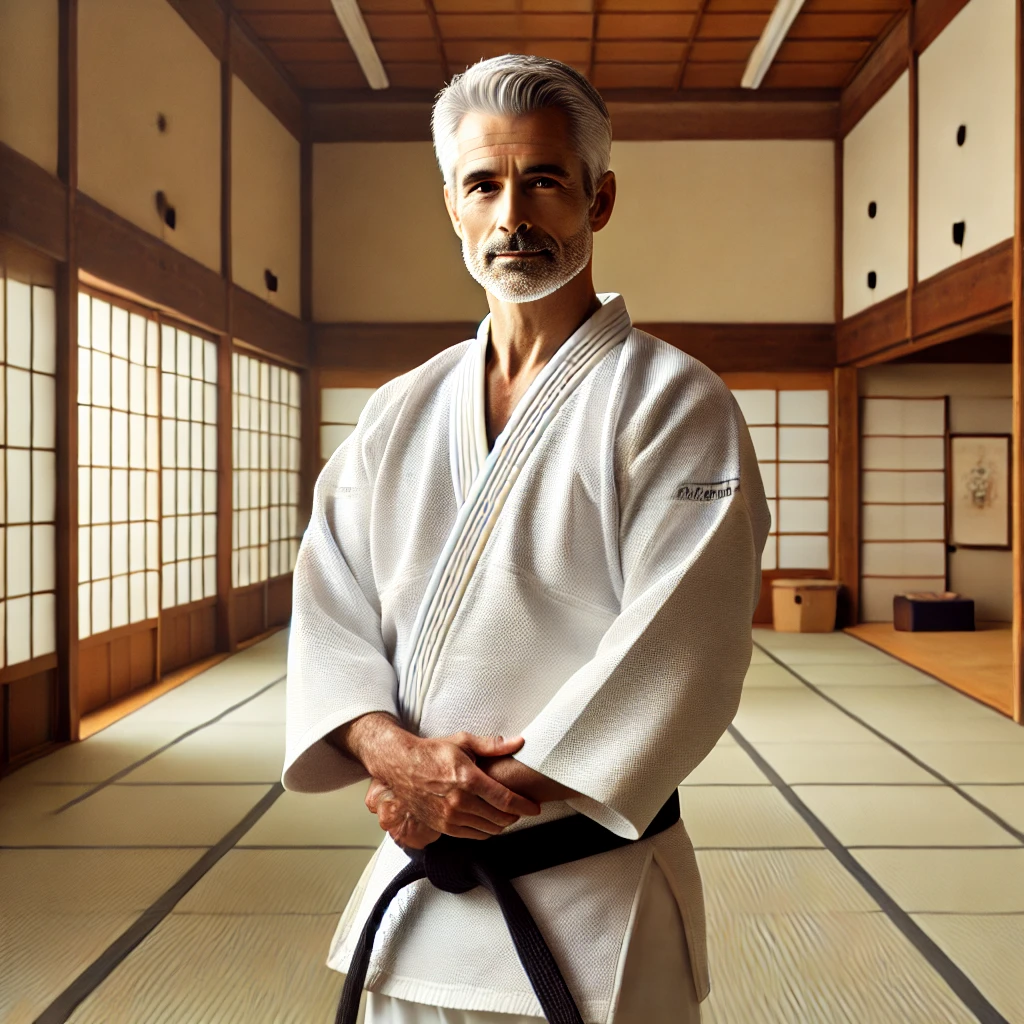
新NISA成長投資枠も利用すべきでしょうか?

成長投資枠は、年間240万円まで投資ができ、株式やETFのような成長性の高い商品が対象です。
ただし、50代ではリスクを抑えることが大切なので、安定的な商品を中心に選ぶと良いでしょう。
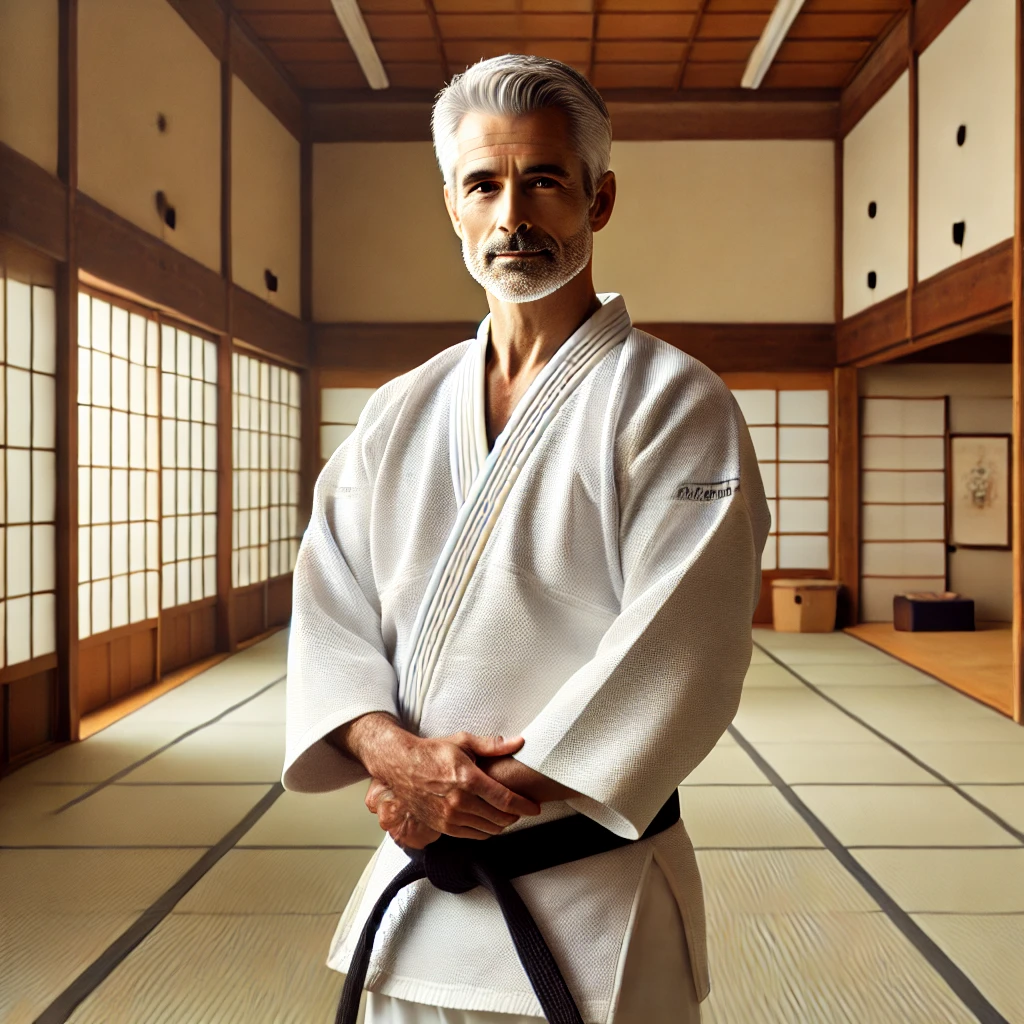
非課税枠を使い切った後はどうすれば良いですか?

非課税枠を使い切ったら、特定口座一般枠を活用してください。
ここでは運用益に税金がかかりますが、分配金や配当金を受け取る商品を選ぶことで、定期的な現金収入を得ることができます。
もちろん新NISA 成長投資枠を高配当株式や分配金が出る投資信託(毎月分配金を除く)に充てて配当金や分配金を非課税にする事も出来ます。

分配金や配当金を活用した商品
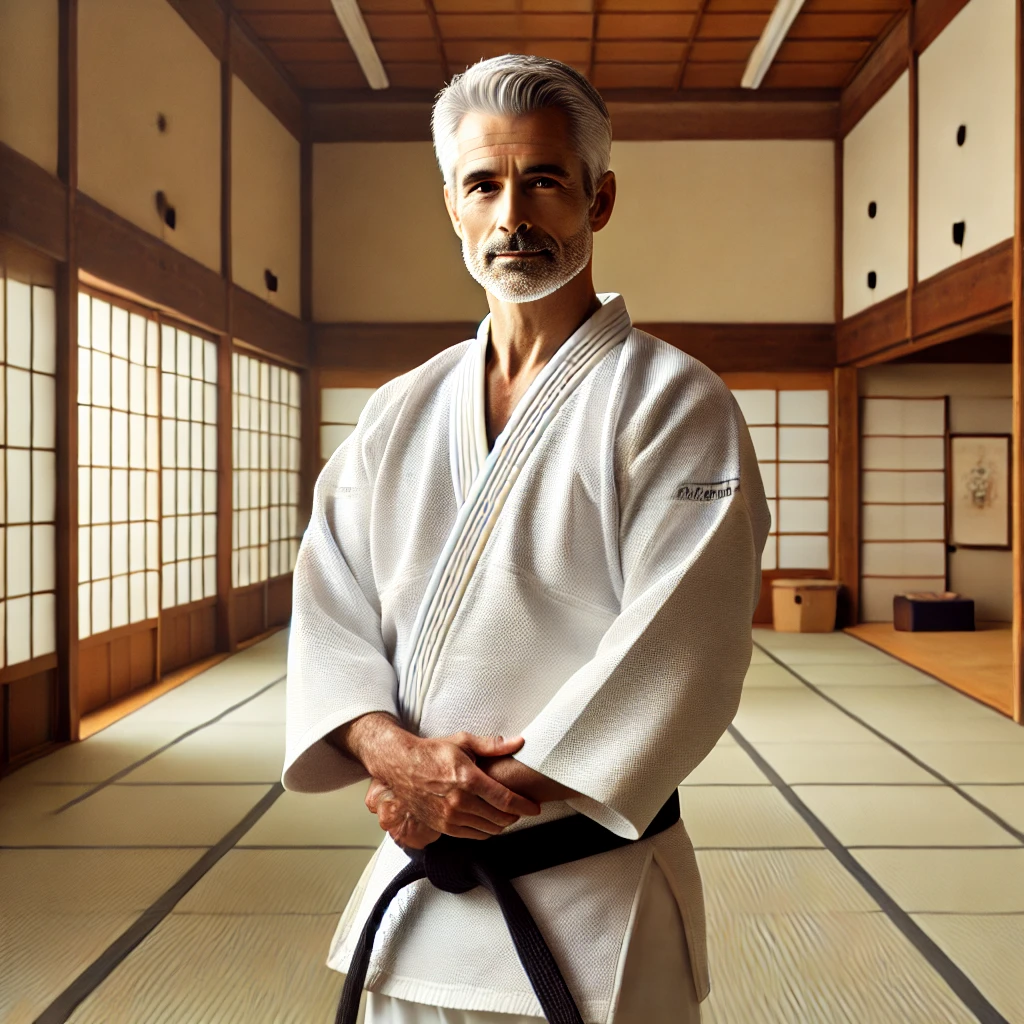
分配金や配当金が得られる商品はどんなものがありますか?

具体的には、分配型の投資信託や配当利回りが高い株式があります。
これらをポートフォリオに組み入れることで、道場運営や生活費に充てる定期収入を得ることができます。
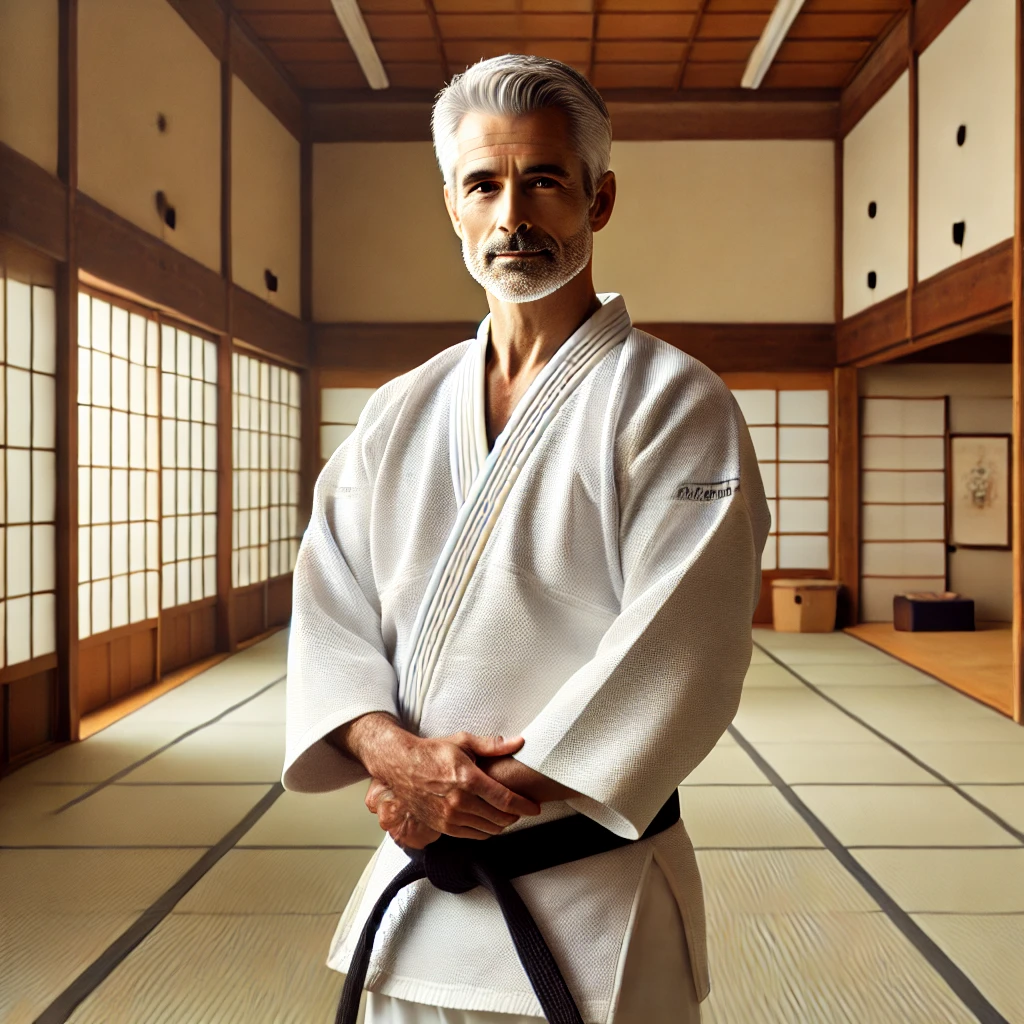
デメリットはありますか?

分配金や配当金には税金がかかるため、手元に残る金額が減ることがあります。
また、元本が減るリスクもあるので、必要な収入とリスクのバランスを考えながら選びましょう。

債券や安全性の高い商品へのリバランス
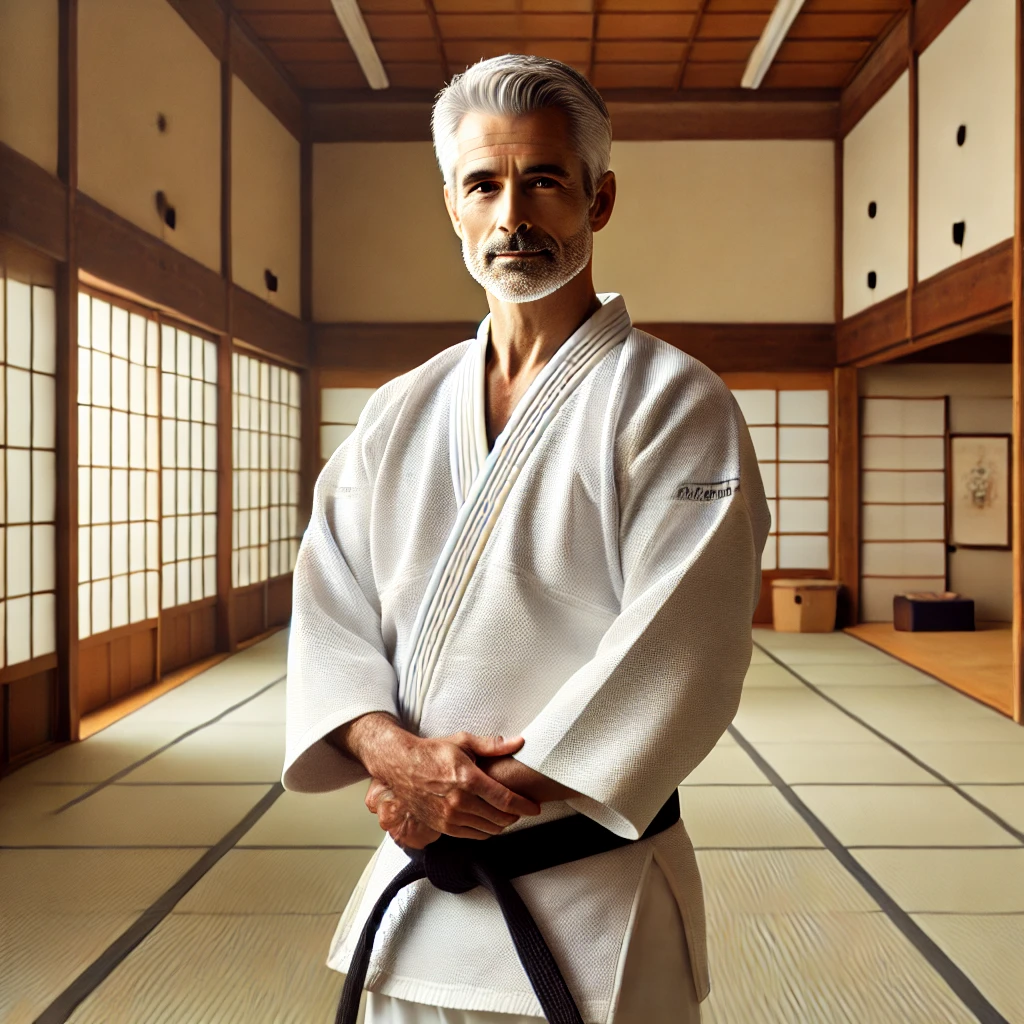
安全性の高い商品にはどんなものがありますか?

債券や債券型の投資信託が代表的です。
これらは株式よりリスクが低く、定期的な利息収入が得られるのが特徴です。
また、日本国債や社債など、比較的安定した商品を選ぶと良いですね。
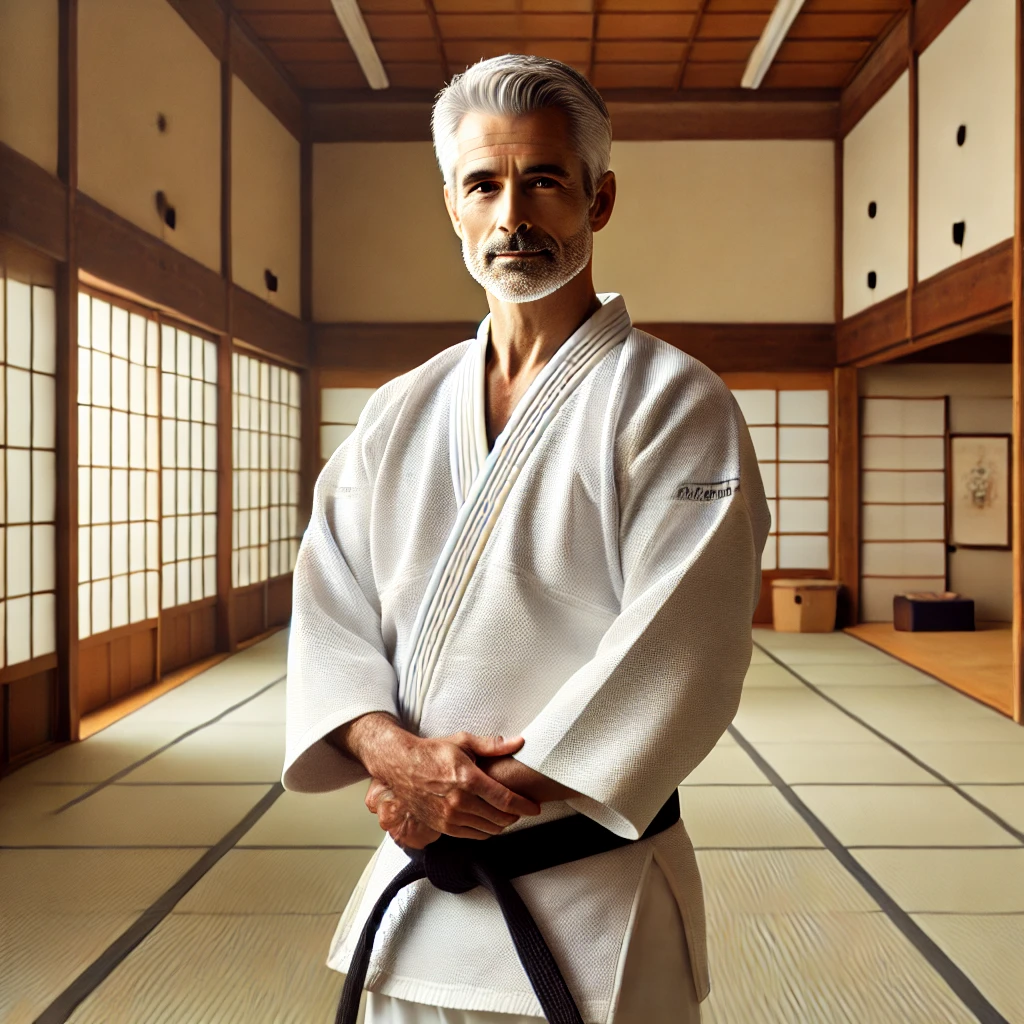
それらをどのくらい組み入れるべきですか?

50代では、資産全体の30~50%を安全性の高い商品に割り当てるのが一般的です。
運用方針や必要な資金に応じて調整してください。

小規模企業共済
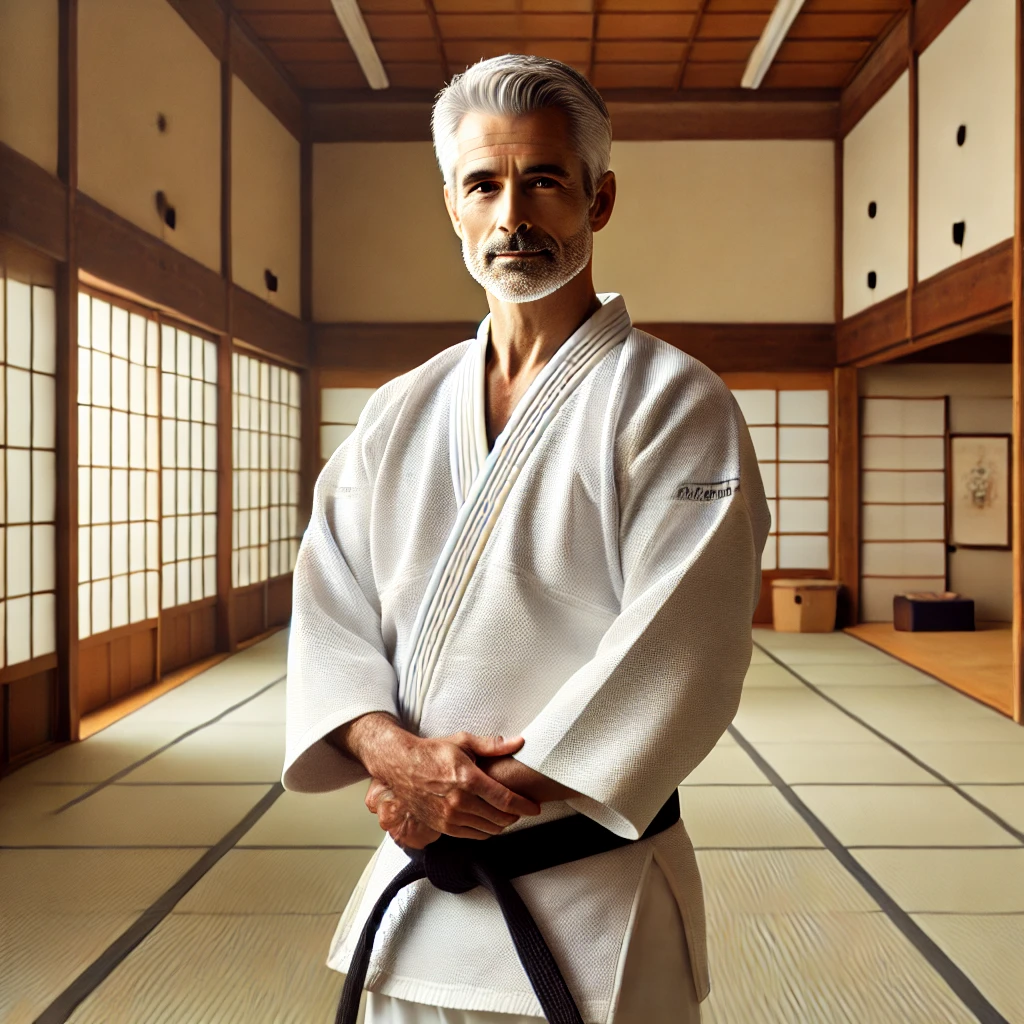
小規模企業共済は今からでも利用する価値がありますか?

もちろんです。掛け金が全額所得控除の対象になるため、節税しながら退職金を準備できます。
50代は、退職に備えたまとまった資金の準備を本格化させる時期なので、特に有効な制度です。

まとめ
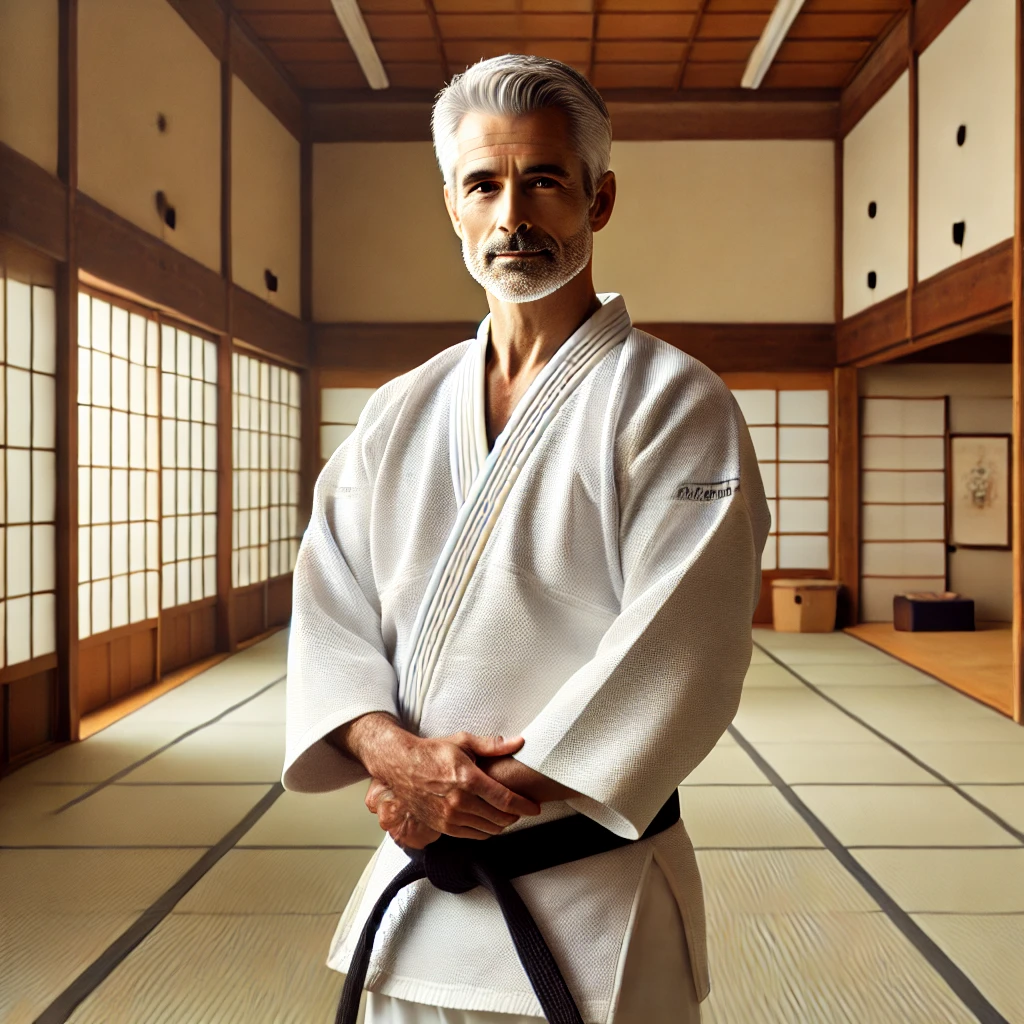
分配金が得られる商品や安全性の高い債券を取り入れる必要があることがわかりました。
老後に向けて計画的に運用を進めたいです。

その通りです。
50代は資産運用を安定性重視にシフトする時期です。
リスクを抑えつつ、定期的な収入を得られる運用を組み合わせて、安心して老後を迎えましょう。
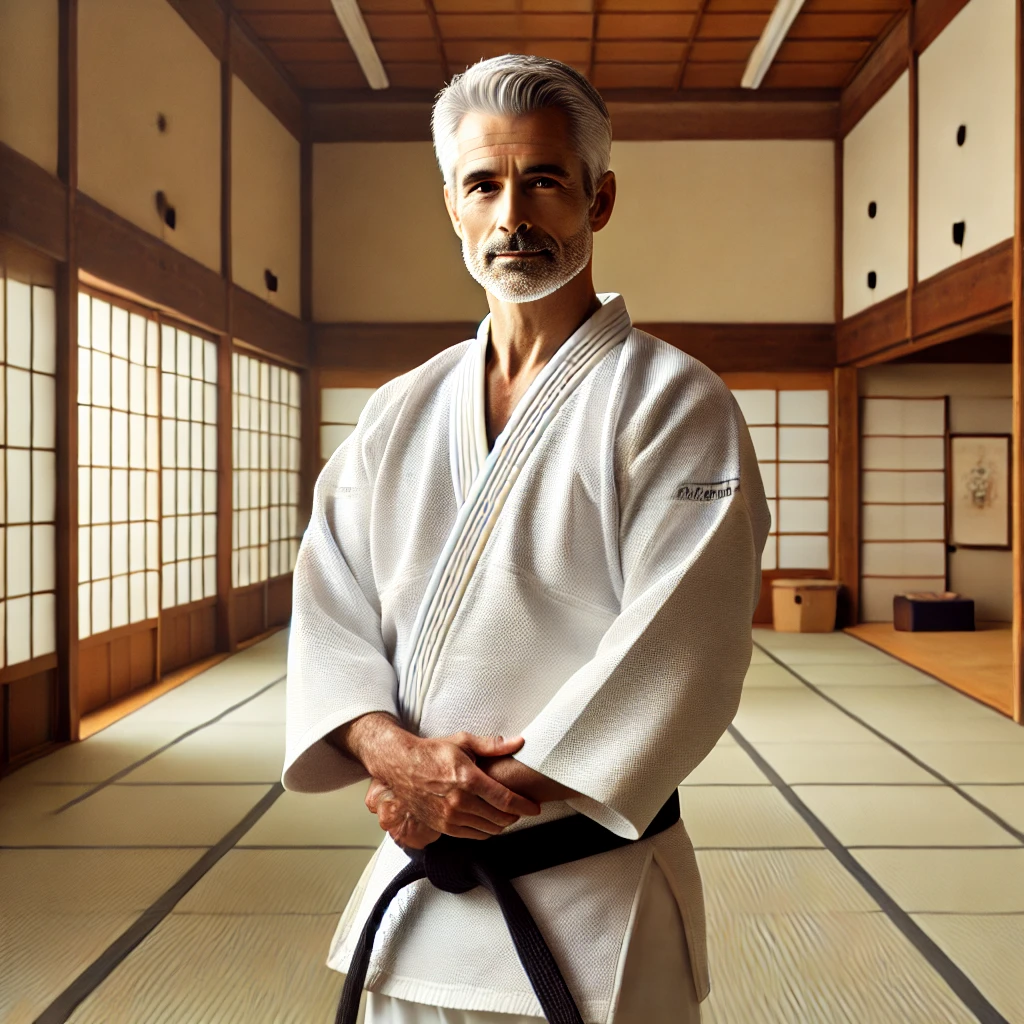
まずは新NISAのつみたて投資枠を活用して、少しずつリバランスを進めていきます。

素晴らしい選択です。
計画的な運用を続ければ、道場経営とご自身の将来をしっかり支える資産が築けるはずです。
50代の道場長にとって、資産運用は老後の安定と道場経営を支える重要な手段です。
この時期には、これまでの資産形成から安全性を重視した運用へリバランスし、分配金や配当金を得られる商品を組み入れることで、収入を安定させることが大切です。
新NISAつみたて投資枠や成長投資枠、小規模企業共済、債券型の投資を活用し、計画的に資産を管理しましょう。
資産運用は継続が鍵です。安心して老後を迎えるために、今から一歩ずつ準備を進めていきましょう!
- 本記事の内容は執筆時点(2024年12月)の情報に基づいています。
そのため、法制度や金融商品の詳細については、最新の情報を必ずご自身で確認してください。
また、資産運用はリスクを伴う場合があり、最終的な意思決定は自己責任で行っていただくようお願いいたします。
本記事の内容に基づくいかなる損失やトラブルについても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
.png)